
ミンガス・アット・モンタレイ
“ジャズ語”なるものがあると聞いたことがある。ミュージシャン同士で楽器でしゃべることができるのだという。いってみれば動物同士の会話のようなもので、もし自分にもそんな言葉ができるようになったらいいなと思った。そんなことを考えていたのは20年ぐらい前のことなのだが、そのころ、下北沢のジャズ喫茶「マサコ」でこのアルバムを聴いたときに、それまでにない体験をした。1曲目の「エリントン・メドレー」はミンガスのベースソロによる「アイ・ガット・イット・バッド」から始まるのだが、このとき、ミンガスのソロがまるで私に話しかけているように聴こえてきたのだ。
最初は何か遠くでぶつぶつと小さくつぶやいているような感じだったのが、だんだんその声がハッキリと聴こえるようになり、しまいにはミンガスが何を言いたいのかがわかるような気がしてきたのだ。そのときのミンガスは、まるで自分の惚れた女性に向かって求愛をしているようだった。ロマンティックというよりも、どこか弁解じみているというか、「オレはこんな男でこういう不器用な生き方しかできないんだ」みたいなことを切々と訴えかけているように聴こえてきた。それは、音を言葉に翻訳して理解するというよりも、ダイレクトにその意味が脳に伝わってくる、テレパシーのような感じだった。それがジャズ語を話せるということなのかどうかはまったくわからないのだが、ジャズを
聴いていてそんなふうに感じたのは初めてだった。
このアルバムはミンガスのライブアルバムの中でもよく売れているようだし、たしかにいい出来だ。ただ、これよりもっと素晴らしいミンガス・バンドの演奏はいっぱいある。だが、ここで聴ける彼のベース・ソロは、彼のレコーディング・キャリアの中でもベストではないかと思う。

コーネル1964
Disc One
痛々しいほどに瑞々しく、濃い青空のように新鮮だ。生きることの喜びが湧出するのをミンガスに初めて感じ、涙が出た。各プレヤーの演奏も初々しく、純粋で伸び伸びしている。ミンガス色について言えば、現代文明の持つ退廃と自嘲は、彼の音楽の基調で、彼の社会性の所以であり、怒りのベースになっていると思われるが、ここでは、そうした屈折した感情は表出せず、ひたすらジャズの喜びが進行する。陰性面をしいて挙げれば、孤独が語られている位だろう。観客との掛け合いも楽しげだ。
Disc Two
一気に深くなり、ミンガスの本領発揮で、聴き応えがある。1曲目、現代文明の不安・不条理という呪縛をあるがままに受け止めている男気を感じる。ここに嘲笑はなく、彼は真摯だ。2曲目、雄々しいミンガス、勇気。3曲目、一転して軽快になり、“国歌”ならぬ“地球歌”のようだ。4曲目は楽しげな曲で、地球という宇宙のオアシスに生きることのワクワクするような興、力感を覚える。各プレヤーの力演が素晴らしい。
二枚組みの本作は、フレンドリーなミンガスを心から味わえる名品だ。

ジャズ・カントリー (文学のおくりもの ベスト版)
人間誰しも、自分で思っている得意なものがある。人によっては文章がうまかったり、野球がうまかったり、サッカーだったり、英語がしゃべれたり・・・。この物語の主人公の白人少年は、トランペットがうまい。だが、それを自慢にしていた甘いうぬぼれと夢は、憧れの前衛ジャズミュージシャン・ピアニストのモーゼ・モンゴフリーに会い、一言、「お前はミュージシャンか?」という問いかけの前に挫けてしまう。「音楽で自己を語る」という、ミュージシャンとしての覚悟を聞かれたのだが、これに対して、まともに答えることができないわけだ。そんな「ボク」が、モンゴフリーや仲間達と出会いながら、自己表現としての音楽(ジャズ)を発見していく様を描く青春小説、それが、この「ジャズカントリー」だ。今、何がしかの仕事を始めてすでに二十数年経つ自らの姿を省みると、得意なはずの仕事や趣味などで、どれだけ自分を表現しているか、はなはだ疑問なのだが、そんな自分に対してもまだ何かを探せる気力を思い出させてくれる一冊だと思っている。何か好きなものがある全ての人々にオススメの本。
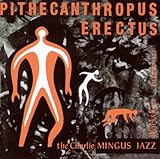
直立猿人
モダン・ジャズはおそらくふたりの奇才を生んだ。天才的なコンポーザーにして類まれな演奏者セロニアス・モンク(p)とチャールス・ミンガス(b)だ。ともに時代の中で周囲からひときわ離れた別の山脈として聳え立ち、特異な作曲、編曲の才能と追随者を寄せ付けない全く持ってユニークなテクニックで演奏をする。ミンガスはモンク同様ビ・バップ・エイジから活躍しているベースの巨人だが、単なるベーシストというより、ジャズを芸術に高めた功績者というべきであろう。とりわけ直立猿人というアルバムはまるで抽象絵画を見るような見事な色彩感に彩られた音の浮遊に驚かされる。ジャッキー・マックリーンとJ.R.モンテローズの二本のアルト・サックスの音色がまるでチューブから搾り出した絵の具のように空間にたち現れる。音の視覚化をこれほどまでに具現化させた音楽家はそうはいない。霧深き日では、サンフランシスコの情景を思い起こさせる映像的サウンドが充満し否が応でも車の往来する霧深き町のイメージが感じられる。このような用語は存在しないが、アブストラクト・ジャズとでも命名したくなるミンガスの構成音楽の世界に我々は完全にはまってしまうのである。

Mingus at Carnegie Hall
74年のライブ盤。バンドリーダーとして、いつもは強力な支配力を発揮するミンガスが、サポートに徹した熱すぎるジャム。
何せメンバーが、ローランド・カークにジョン・ハンディ、ジョージ・アダムス、チャールス・マクファーソン、ジョン・ファディス、ドン・プーレン、ダニー・リッチモンドだ。特にカークは珍しくワンホーンのみで、彼の演奏でもベストのひとつといえる熱演。他の面々も熱いソロを取っている。
驚きはソロがないミンガスのベースだが、これが地を揺るがすような、腹の底から響くような、あのミンガス・ベースラインでメンバーをサポート。これが実に気持ちいい。ミンガスほど、聴いていて心地よく昂ぶるベースはないと思うのだが、どんなものだろう。
何はともあれ、ジャズメンたちの熱気がそのまま伝わるような超名盤。ミンガスのメッセージ性やバンドリーダーとは違った魅力が全開である。






