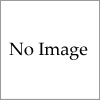蟹工船・党生活者 (新潮文庫)
「蟹工船」の中の過酷な労働・非効率性・非衛生的な労働環境の中、監督は漁夫・雑夫達を厳しく働かせるが、やむにやまれず労働者がサボタージュやストライキをしていく過程をいきいきとするどい描写で書き綴られていて、読んでいて圧倒される。会社は会社の命を受け忠実に業務を遂行していた監督を、ストライキを惹き起こした責任をとらせる処分として首を切り、監督は会社に裏切られたという忸怩たる思いをしなければならかった、これは現在でもかわっていないと思います。「党生活者」は、地下生活者として活動し続ける著者の命がけの闘争の記録で、帝国主義日本で何か発言したり主張しようとする人間が、なぜ地下生活をしなければならないのか、考えさせられました。現在は表現の自由はあるものの、会社の論理に個人生活は組み込まれ、人間的生活ができない状況はかわらないと思います。筆者の時代の記録を参考に、現在を生きる私たちはこれから何もすべきなのか、自分に問うべきだと思います。

母 (角川文庫)
小樽で小林多喜二の文学碑を見た感動を、今も忘れることはできない。
「冬が近くなるとぼくはそのなつかしい国のことを考えて深い感動に捉られている (中略) 赤い断層を処々に見せている階段のように山にせり上がっている街をぼくはどんなに愛しているか分からない」
このような、自らが住む街を深く愛した先人を持つ小樽市民を、どんなにか羨ましく思ったことか。
多喜二の母から見た多喜二の生涯と著者から見たその母の生涯、キリスト教という信仰を共にする三浦綾子が書いた感動の作品。
「蟹工船」に代表されるプロレタリアート文学の旗手であり、共産主義者、そして最後には特高警察の拷問により齢30で非業の死をとげた、多喜二の人生を母の視点から描いてゆく。
虐げられた労働者の側に立ち、自らの目の前で繰り広げられれた非人道を決して許容できなかった、愚直なまでの多喜二の姿勢は、この母の人間性なくしては決して生まれることはなかった。
小林多喜二本人や、プロレタリアート文学、共産主義といったものに知識がある必要はまったくありません。そんな知識が無くとも十二分に読める作品です。どうか、お子さんを持つお母さんにも先入観なく読んで欲しい。涙がページを濡らすことでしょう。
彼女は晩年に洗礼を受けキリスト教に入信した。自己を犠牲にして小さき者、貧しき者に尽した多喜二をその殉教の精神と重なり、まさに神の子と感じたに違いない。
彼女は共産党に入党しながらも、葬儀はキリスト教式で行うことを強く切望したそうだ。
確かに小林多喜二は「神の子」だったに違いない。

蟹工船 (まんがで読破)
現在マスコミに採り上げられて話題になっているが、本来は社会主義の幻想が解けた現代にプロレタリア文学はそぐわないはずだった。しかし、文学ではなくマンガとして作品化した場合、結構いけると思ったのが今回の本である。劇画調のタッチで書かれていてキャラクターがかなりデフォルメされてわかりやすく滑稽でさえある。当時の社会風潮を知らなくても一つの作品として十分楽しめると思った。もし原作が読みたくなるのであれば、読書への取っ掛かりとしてマンガから入るというのはいいかもしれない。